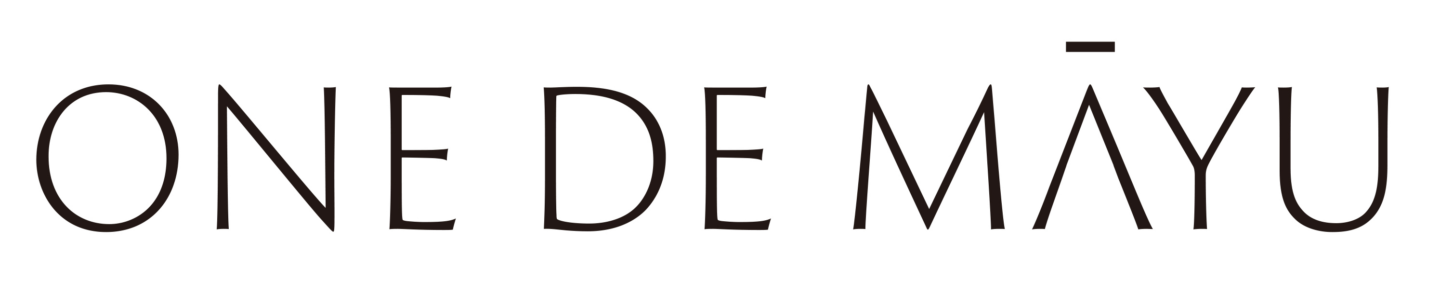今回はジェンダーダイバーシティ(性の多様性)についてご紹介します。
ジェンダーとは、社会的・文化的につくられた性の差異のことを指します。
ジェンダーは、LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)など性のあり方が多様化しています。
性別とは、男女の2つだけの選択肢ではありません。
ジェンダーギャップ指数 2021から見えるもの
ジェンダーギャップ指数とは、ジェンダー間の差別を図る指標のことで、経済・政治・教育・健康の4分野に分かれています。
日本のジェンダーギャップ指数は、150カ国中120位(2021年)と、中国や韓国、ASEAN諸国よりも低く、先進国の中では最低レベルです。

ジェンダーギャップ指数が低いことの意味
· 女性や性的マイノリティの心身のウェルネス侵害
女性は生理や妊娠、出産などライフイベントに左右されやすく、生活面での負担が大きいため、仕事とのバランスを取ることが難しい状況があります。
· 女性や性的マイノリティの経済的負担が大きい
女性は育児や仕事との両立が難しいため、昇格を諦める、再就職しにくく経済的に不安定な場合が少なからずあります。
また、男女間での平均年収239万円の差も大きな問題です。
同じ仕事量、仕事時間でも女性の方が少ない対価を受け取っています。
日本は特に、経済と政治分野のジェンダーギャップ指数が低く、性差が顕著に残っています。
【経済分野 ジェンダーギャップ】
· 管理職の女性は14.7%
· 女性の所得は男性より43.7%低い
· パートの割合が男性の2倍
· コロナによりさらに女性やマイノリティの経済的負担が増加
ジェンダーギャップはコロナにより加速している現状があります。
コロナの影響で、女性は特に離職や休業を余儀なくされ、精神的にもつらい状況にあります。
警察庁によると、2020年10月の女性の自殺率の増加は、前年より82.6%も増加しています。
コロナが女性の生活に多大な影響を与えたことがうかがえます。
【政治分野 ジェンダーギャップ】
· 女性の低政治参加の割合
· 国会議員の女性の割合 9.9%
政治参加におけるジェンダーギャップが大きいことが見て取れます。
なぜ日本はジェンダーギャップが大きいのか
日本のジェンダーギャップが大きい一つの要因は、男性優位社会の名残が残っているためと考えられます。
男性は、外でお金を稼ぎ、女性は家の中で家事をするという性別による役割分担が当たり前の時代がありました。
男性の労働は、お金になるものであり、女性がするべき労働は無報酬で、「家庭で男性を支える」という考えが残っているようです。

一見するとジェンダーギャップは、女性や性的マイノリティにとっての問題に見えますが、実は男性にも関係があります。
性的役割分担やジェンダーの固定観念にしばられると、「家族を養うために働かなくては」と重い責任がのしかかります。
コロナ禍や文明転換の不安定な現代では、終身雇用制などの安泰は望めません。
責任を共有し、負担を分け合うと、楽しさは倍になります。
ジェンダーの多様性について考える
ジェンダー平等とは、単に女性の社会進出が進むことではありません。
女性の社会進出が進む一方で、女性は家庭内での仕事を当然のことのように請け負います。

これでは女性の社会的負担が増えるだけです。
大切なことは、仕事や生活面、家庭内での仕事を分かち合って生きること。
ジェンダーダイバーシティ(性の多様性)を尊重し、相手の気持ちになって考えることが大切です。